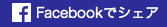���{/�n��NPO�x���i���J���F2024.07.05�j
�y����J�n�z���{������NPO���������u�q�ǂ��E�n�您������t�@���h�v��3�� �\����t9��2���܂�
�Z�[�u�E�U�E�`���h�����́A���{�����Ŏq�ǂ��x���������s���n�����c���c���iNPO�j��ΏۂƂ����A�����v���O�����u�q�ǂ��E�n�您������t�@���h�v��3�������J�n���܂����B�q�ǂ��Q���𐄐i���Ȃ���A�n��ł̎q�ǂ��̌����ۏ��ڎw������ ���T�|�[�g���܂��B
���Ђ��\�����������B
���ڂ�����������
�������T�v
���{�e�n�Ŏq�ǂ��̕�炵��炿�A�܂Ȃт��x�����c���̊������������A�܂��A�����ʂ��Ďq�ǂ������̈�����I�ɉ��P���Ă������Ƃ�ړI�Ƃ��������v���O�����ł��B
�q�ǂ��A�ی�ҁA�q�ǂ��x���W�҂̂��߂Ɋe�n�Ŋ�������c�̂L���ΏۂƂ��A���̎��Ƃ�g�D�^�c�݂̍�����Ƃ��ɍl���A������g�D�^�c�ɉ����A�c�̂̊����ɂ�����q�ǂ��̌����ۏ�̂��߂̊��Â�����T�|�[�g���Ă����܂��B
�y�����n��z���{����
�y��������z�q�ǂ��Q���𐄐i���Ȃ���A�q�ǂ��̌����ۏ��ڎw���������L���ΏۂƂ��܂��B���Ɏ��̕�������}���܂��B
�E�q�ǂ��̕n�����̉���
�E�q�ǂ��s�҂̗\�h�A�s�҂�s�K�ȗ{������q�ǂ��ւ̎x��
�E�ЊQ���̎q�ǂ��̕ی�̂��߂̎��g�݁A�q�ǂ��ƂƂ��ɐi�߂�h��
�y�����̑Ώێҁz �q�ǂ��i18�Ζ����j����т����ی���A�q�ǂ�����芪����l�B���ɁA���{�����Ŏ��c���ꂪ���Ǝv������ɂ���q�ǂ���A�q�ǂ�����芪����l�Ɍ������������d�����܂��B
�y�x�����e�z������c�̂ɑ��A���́i1�j�`�i3�j�����ׂčs���܂��B
�i1�j�������� 1�c�� 1�N������200���~�`300���~�i�����N�����j
�i2�j�g�D��Ջ����̂��߂̎��g��
�i3�j�q�ǂ��̌����ۏ�̂��߂̊��Â���
�y�x�����ԁz2025�N1���ȍ~�`2027�N9���i�Œ��j
�y�\�����ԁz2024 �N6��28���i���j�`2024�N9��2���i���j
���I�����C�����������i���O�\�����ݐ��j
��������肨�\�����݂��������B
�E��1�� 2024�N7��13���i�y�j10:00�`12:00
�E��2�� 2024�N7��16���i�j13:00�`15:00
���{�t�@���h�̑I���̒��ōł��d������u�q�ǂ��Q���v�ɂ��Ẵ��[�N���s���܂��B
���ǂ���̉�����e�͓���ł��B�܂��A���{��ɘ^������J����\��ł��B
�y�₢���킹��z
���v�Вc�@�l�Z�[�u�E�U�E�`���h�����E�W���p�� �������ƕ� �n��NPO�x������
�S���F���p�i�����݁j�E���i���ǂ���j
Email: japan.cn@savethechildren.org