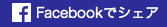���{/�����ЊQ�i���J���F2024.11.07�j
�y12��16�����߂܂Ő\����t���z2024�N�\�o�����n�k�E���J�ً}�����x���u�\�o�q�ǂ��T�|�[�g���t���v
�Z�[�u�E�U�E�`���h�����́A2024�N1��1���ɔ��������\�o�����n�k�����9���̉��\�o���J�̉e���ɂ��i���E�i�w��A�E�Ɍ����������ȂǂɎx�Ⴊ�Ȃ��悤�A���Ў��ɐΐ쌧�����s�A�������A�\�o���A��F�s�A�֓��s�̂����ꂩ�ɍݏZ���A��Џ̈��̏����������ݏ��w6�N�����獂�Z������̎q�ǂ��ɑ��ċ��t����������܂��B
���t���e��\�����@�Ȃǂ̏ڍׂɂ��ẮA���L�����m�F���������A�Ώۂɓ��Ă͂܂���́A���Ђ��\���݂��������B�܂��A���͂őΏۂɓ��Ă͂܂���������m�̕��́A���Ў��m�ւ̂����͂����肢�������܂��B

�y�w�i�z
2024�N1��1���ɔ��������\�o�����n�k�Ɋւ��A�Z�[�u�E�U�E�`���h�����͏����A�q�ǂ��̕ی�A����A������̃P�A�̊ϓ_���炳�܂��܂Ȋ�����W�J���Ă��܂����B���Ђ���1�N���߂Â����A�q�ǂ������̌ʂ̃j�[�Y�����݉����Ă��Ă��܂��B���ɏ��w�Z���w�N���獂�Z������ɂ��ẮA�w�Z�ł̊w�т╔�����A�K������m�A�����E�X�|�[�c�����Ȃǂ̉ۊO�����A�i�H�I���ȂǁA���l�Ȍo���̂��߂̔�p�������邱�Ƃ������܂�܂��B
9���ɔ����������\�o���J�ɂ��A��������������o���ւ̌o�ϓI���S���܂��܂��傫���Ȃ钆�A�q�ǂ������̌ʂ̃j�[�Y���[�����A��Ђ����n��Ŏq�ǂ������������炵���w�сA�������ۏႷ�邽�߁A�Z�[�u�E�U�E�`���h�����́A�q�ǂ��Ɋւ���p�ւ̌o�ϓI�x���u�\�o�q�ǂ��T�|�[�g���t���v�����{���܂��B
�y�Ώێҁz
�ȉ��̗v��1�A2�����ɂ��Ă͂܂鐢�т̌��ݏ��w6�N���܂��͒��w�Z�A���Z�Ȃǂɍ݊w���Ă���q�ǂ�
���w�Z�́A�������i�����E�s���Ȃǁj����ю����A���ʎx���w�Z�A�ʐM���E�莞�������w�Z�A��������w�Z�A�������w�Z�Ȃǂ̊w�Z�i����Z�F�w�Z����@�����ɊY������w�Z�������j�ɉ����A����Z�ȊO�̊e��w�Z�A�O���l�w�Z�A�t���[�X�N�[�����܂݂܂��B
1�D2024�N1���̔\�o�����n�k��������9���̉��\�o���J�������ɐΐ쌧�����s�A�������A�\�o���A��F�s�A�֓��s�̂����ꂩ�ɍݏZ�i��Џؖ��Z�������L5�s�����A�Z�[�u�E�U�E�`���h���������n��j
2�D2024�N1���̔\�o�����n�k��������9���̉��\�o���J�ɂ��ЊQ�����Z���Ă����Z��ꕔ����E������E����E���K�͔���E��K�͔���E�S��̂����ꂩ�ɔF��
�����݁A��L�̎s���ȊO�ɔ��E�����z���������т̎q�ǂ����ΏۂɂȂ�܂��B
�y���t���e�z
�q�ǂ���l�ɂ��ꗥ3���~�i�Ԋ҂̕K�v�Ȃ��j
����L�\�����������Ă���A���傤�����܂Ƃ߂Ă��\�����݂��������܂��B
�y�\�����ԁz
2024�N11��1���i���j���߁`12��16���i���j����
�������I�����C���ł̐\���ƂȂ�܂��B��ނȂ��������ꍇ�̂ݗX�����t���܂��B�X���̏ꍇ��12��16���i���j�K���ƂȂ�܂��B����L���ł͂���܂���̂ł����ӂ��������B
���\���t�H�[����o�������͏��ޓ�����A3�T�Ԓ��x�ŔF��E�U���̎葱�����s���܂��B
���\�����Ԃ��߂����ꍇ�́A�ǂ̂悤�ȗ��R�������Ă��t���邱�Ƃ͂ł��܂���̂ł��������������B
�y�K�v���ށz
�ȉ��̏��ނ��������̂����A�\���t�H�[������ʐ^�܂��̓X�L�����f�[�^��Y�t���Ă��������B
1.�ΏۂƂȂ�q�ǂ��������鐢�т̏Z���[�i���ёS�����j
�������K�v�i�ȗ��s�j�A���s����2024�N10��28���ȍ~�̂��́A�}�C�i���o�[�s�v�B
2.�ΏۂƂȂ�q�ǂ��������鐢�т̜�Џؖ���
��2024�N1���\�o�����n�k�A9�����\�o���J�A�����̍ЊQ�Ŕ�Ђ��ꂽ�ꍇ�́A�ǂ��炩����̜�Џؖ��������p�ӂ��������B
�y�\�����狋�t�܂ł̗���z
1.�\���ҁF��L��ǂݑΏۏ����ɍ����Ă��邩�m�F���A�\���ɕK�v�ȏ��ނ�p�ӂ���B
���ڍׂ́y�Ώێҁz�y�K�v���ށz�̍��ڂ����m�F���������B
2.�\���ҁF�ȉ��̐\���t�H�[�����K�v��������͂��A�K�v���ނ̃f�[�^��Y�t���đ��M����B
�\���t�H�[����������
���I�����C���̐\��������ꍇ�́A�₢���킹�t�H�[���ɗ��R���������̂������₢���킹���������B
3.�Z�[�u�E�U�E�`���h�����F�\���t�H�[���̓��e�ƕK�v���ނ����ƂɔF��̉ۂ�B
�F��̏ꍇ�A�O�������T�[�r�X�ƎҁuGMO�y�C�����g�Q�[�g�E�F�C������Ёv���F�萢�тɁA���t�����t�̂��߂̌������̈˗��ʒm�����[���ő��M�B
�F�肳��Ȃ������ꍇ��A�������Ȃ������ꍇ�́A�Z�[�u�E�U�E�`���h��������\�����т֘A���B
���\���v����������ŁA���e�ɕs���E���U���Ȃ��A�K�v���ނ��Y�t����Ă���A�����F��ƂȂ�܂��B
4.�\���ҁF�uGMO�y�C�����g�Q�[�g�E�F�C������Ёv����̃��[���Ɍ�������A���B
5.�Z�[�u�E�U�E�`���h�����F�����w������ɓ����B�i�\����A3�T�Ԉȓ���ړr�j
�y��W�v���z
��W�v����PDF�t�@�C���́A��������������m�F�A�_�E�����[�h���ł��܂��B
�y�₢���킹��z
���v�Вc�@�l�Z�[�u�E�U�E�`���h�����E�W���p���������ƕ��u�\�o�q�ǂ��T�|�[�g���t���v�S��
��101-0047�����s���c����_�c2-8-4�R�c�r��4�K
�₢���킹�t�H�[����������
Email: japan.notosupport@savechildren.or.jp
���l���̕ی�ɂ��� �F
�Z�[�u�E�U�E�`���h�����́A������ʂ��Ď擾�����S�Ă̌l���̏d�v����F�����A���@�l�́u�v���C�o�V�[�|���V�[�v�Ɋ�Â��A�l���ی�@���͂��߂Ƃ���W�@�߂���ъ֘A�K�C�h���C�������炵�āA�l�̌����ی�ɓw�߂܂��B
�\�����Ɏ擾�����l���́A�{���t���̎��{�ɕK�v�ȘA���E�葱���A�Z�[�u�E�U�E�`���h�������s�����̊����◘�p�\�ȃT�[�r�X�Ȃǂ̐\���҂ւ̏��A�A���P�[�g�E�C���^�r���[�������{�Ȃǂɗ��p���A���@�l���ӔC�������ĊǗ��E�ۊǂ��܂��i�ۊNJ����͋��t�I����5�N�j�B�\���҂̏����Ȃ���O�҂Ɍl������邱�Ƃ͂���܂���B
�Ȃ��A�\�����̐R���⋋�t���̑����Ɋւ��āA���@�l���Ɩ��ϑ��_�������ƂȂǂɁA���e�̎�舵�����ϑ�����ꍇ������܂����A���̏ꍇ�ɂ��A�F�l�̌l���͓��@�l�̌l���ی쌴���̂��Ƃŕی삳��܂��B�܂��A�\������W�v���ʂ������E�Љ�[���E�����E�L���ȂǓ��@�l�̊����Ɏg�p���邱�Ƃ�����܂����A�l�����肳���`�Ō��\����邱�Ƃ͈����܂���B���@�l�̃v���C�o�V�[�|���V�[�����������������������B
------------------------------------------
�q�ǂ�������ی�҂̐��A�����A����t�̕��@��������
���t���e��\�����@�Ȃǂ̏ڍׂɂ��ẮA���L�����m�F���������A�Ώۂɓ��Ă͂܂���́A���Ђ��\���݂��������B�܂��A���͂őΏۂɓ��Ă͂܂���������m�̕��́A���Ў��m�ւ̂����͂����肢�������܂��B

�y�w�i�z
2024�N1��1���ɔ��������\�o�����n�k�Ɋւ��A�Z�[�u�E�U�E�`���h�����͏����A�q�ǂ��̕ی�A����A������̃P�A�̊ϓ_���炳�܂��܂Ȋ�����W�J���Ă��܂����B���Ђ���1�N���߂Â����A�q�ǂ������̌ʂ̃j�[�Y�����݉����Ă��Ă��܂��B���ɏ��w�Z���w�N���獂�Z������ɂ��ẮA�w�Z�ł̊w�т╔�����A�K������m�A�����E�X�|�[�c�����Ȃǂ̉ۊO�����A�i�H�I���ȂǁA���l�Ȍo���̂��߂̔�p�������邱�Ƃ������܂�܂��B
9���ɔ����������\�o���J�ɂ��A��������������o���ւ̌o�ϓI���S���܂��܂��傫���Ȃ钆�A�q�ǂ������̌ʂ̃j�[�Y���[�����A��Ђ����n��Ŏq�ǂ������������炵���w�сA�������ۏႷ�邽�߁A�Z�[�u�E�U�E�`���h�����́A�q�ǂ��Ɋւ���p�ւ̌o�ϓI�x���u�\�o�q�ǂ��T�|�[�g���t���v�����{���܂��B
�y�Ώێҁz
�ȉ��̗v��1�A2�����ɂ��Ă͂܂鐢�т̌��ݏ��w6�N���܂��͒��w�Z�A���Z�Ȃǂɍ݊w���Ă���q�ǂ�
���w�Z�́A�������i�����E�s���Ȃǁj����ю����A���ʎx���w�Z�A�ʐM���E�莞�������w�Z�A��������w�Z�A�������w�Z�Ȃǂ̊w�Z�i����Z�F�w�Z����@�����ɊY������w�Z�������j�ɉ����A����Z�ȊO�̊e��w�Z�A�O���l�w�Z�A�t���[�X�N�[�����܂݂܂��B
1�D2024�N1���̔\�o�����n�k��������9���̉��\�o���J�������ɐΐ쌧�����s�A�������A�\�o���A��F�s�A�֓��s�̂����ꂩ�ɍݏZ�i��Џؖ��Z�������L5�s�����A�Z�[�u�E�U�E�`���h���������n��j
2�D2024�N1���̔\�o�����n�k��������9���̉��\�o���J�ɂ��ЊQ�����Z���Ă����Z��ꕔ����E������E����E���K�͔���E��K�͔���E�S��̂����ꂩ�ɔF��
�����݁A��L�̎s���ȊO�ɔ��E�����z���������т̎q�ǂ����ΏۂɂȂ�܂��B
�y���t���e�z
�q�ǂ���l�ɂ��ꗥ3���~�i�Ԋ҂̕K�v�Ȃ��j
����L�\�����������Ă���A���傤�����܂Ƃ߂Ă��\�����݂��������܂��B
�y�\�����ԁz
2024�N11��1���i���j���߁`12��16���i���j����
�������I�����C���ł̐\���ƂȂ�܂��B��ނȂ��������ꍇ�̂ݗX�����t���܂��B�X���̏ꍇ��12��16���i���j�K���ƂȂ�܂��B����L���ł͂���܂���̂ł����ӂ��������B
���\���t�H�[����o�������͏��ޓ�����A3�T�Ԓ��x�ŔF��E�U���̎葱�����s���܂��B
���\�����Ԃ��߂����ꍇ�́A�ǂ̂悤�ȗ��R�������Ă��t���邱�Ƃ͂ł��܂���̂ł��������������B
�y�K�v���ށz
�ȉ��̏��ނ��������̂����A�\���t�H�[������ʐ^�܂��̓X�L�����f�[�^��Y�t���Ă��������B
1.�ΏۂƂȂ�q�ǂ��������鐢�т̏Z���[�i���ёS�����j
�������K�v�i�ȗ��s�j�A���s����2024�N10��28���ȍ~�̂��́A�}�C�i���o�[�s�v�B
2.�ΏۂƂȂ�q�ǂ��������鐢�т̜�Џؖ���
��2024�N1���\�o�����n�k�A9�����\�o���J�A�����̍ЊQ�Ŕ�Ђ��ꂽ�ꍇ�́A�ǂ��炩����̜�Џؖ��������p�ӂ��������B
�y�\�����狋�t�܂ł̗���z
1.�\���ҁF��L��ǂݑΏۏ����ɍ����Ă��邩�m�F���A�\���ɕK�v�ȏ��ނ�p�ӂ���B
���ڍׂ́y�Ώێҁz�y�K�v���ށz�̍��ڂ����m�F���������B
2.�\���ҁF�ȉ��̐\���t�H�[�����K�v��������͂��A�K�v���ނ̃f�[�^��Y�t���đ��M����B
�\���t�H�[����������
���I�����C���̐\��������ꍇ�́A�₢���킹�t�H�[���ɗ��R���������̂������₢���킹���������B
3.�Z�[�u�E�U�E�`���h�����F�\���t�H�[���̓��e�ƕK�v���ނ����ƂɔF��̉ۂ�B
�F��̏ꍇ�A�O�������T�[�r�X�ƎҁuGMO�y�C�����g�Q�[�g�E�F�C������Ёv���F�萢�тɁA���t�����t�̂��߂̌������̈˗��ʒm�����[���ő��M�B
�F�肳��Ȃ������ꍇ��A�������Ȃ������ꍇ�́A�Z�[�u�E�U�E�`���h��������\�����т֘A���B
���\���v����������ŁA���e�ɕs���E���U���Ȃ��A�K�v���ނ��Y�t����Ă���A�����F��ƂȂ�܂��B
4.�\���ҁF�uGMO�y�C�����g�Q�[�g�E�F�C������Ёv����̃��[���Ɍ�������A���B
5.�Z�[�u�E�U�E�`���h�����F�����w������ɓ����B�i�\����A3�T�Ԉȓ���ړr�j
�y��W�v���z
��W�v����PDF�t�@�C���́A��������������m�F�A�_�E�����[�h���ł��܂��B
�y�₢���킹��z
���v�Вc�@�l�Z�[�u�E�U�E�`���h�����E�W���p���������ƕ��u�\�o�q�ǂ��T�|�[�g���t���v�S��
��101-0047�����s���c����_�c2-8-4�R�c�r��4�K
�₢���킹�t�H�[����������
Email: japan.notosupport@savechildren.or.jp
���l���̕ی�ɂ��� �F
�Z�[�u�E�U�E�`���h�����́A������ʂ��Ď擾�����S�Ă̌l���̏d�v����F�����A���@�l�́u�v���C�o�V�[�|���V�[�v�Ɋ�Â��A�l���ی�@���͂��߂Ƃ���W�@�߂���ъ֘A�K�C�h���C�������炵�āA�l�̌����ی�ɓw�߂܂��B
�\�����Ɏ擾�����l���́A�{���t���̎��{�ɕK�v�ȘA���E�葱���A�Z�[�u�E�U�E�`���h�������s�����̊����◘�p�\�ȃT�[�r�X�Ȃǂ̐\���҂ւ̏��A�A���P�[�g�E�C���^�r���[�������{�Ȃǂɗ��p���A���@�l���ӔC�������ĊǗ��E�ۊǂ��܂��i�ۊNJ����͋��t�I����5�N�j�B�\���҂̏����Ȃ���O�҂Ɍl������邱�Ƃ͂���܂���B
�Ȃ��A�\�����̐R���⋋�t���̑����Ɋւ��āA���@�l���Ɩ��ϑ��_�������ƂȂǂɁA���e�̎�舵�����ϑ�����ꍇ������܂����A���̏ꍇ�ɂ��A�F�l�̌l���͓��@�l�̌l���ی쌴���̂��Ƃŕی삳��܂��B�܂��A�\������W�v���ʂ������E�Љ�[���E�����E�L���ȂǓ��@�l�̊����Ɏg�p���邱�Ƃ�����܂����A�l�����肳���`�Ō��\����邱�Ƃ͈����܂���B���@�l�̃v���C�o�V�[�|���V�[�����������������������B
------------------------------------------
�q�ǂ�������ی�҂̐��A�����A����t�̕��@��������